3月9日は試薬の日
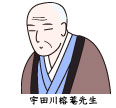
日本ではじめて試薬という言葉を使った幕末の津山藩医で蘭学者の「宇田川榕菴(うだがわ ようあん)」(1798〜1846)の生誕日に因んで、一般社団法人日本試薬協会が、3月9日を『試薬の日』に制定しました。
■「試薬」という言葉の生みの親
宇田川榕菴は、天保3年(1832年)に試薬一覧の「舎密(せいみ)試薬編」を著し、ここで日本で初めて試薬という言葉を使いました。後に欧州の化学書を翻訳した「舎密開宗(せいみかいそう)」では、試薬使用凡例にかなりの試薬を挙げてその使い方や注意を記しています。
※舎密(せいみ)とは、「化学」を意味するオランダ語Chemieの字訳です。
■お馴染みの化学用語も
試薬をはじめ、「酸素、水素、窒素、炭素、白金」という元素名や、「酸化、還元、分析」といった日本における化学用語のほとんどは宇田川榕菴が考えたといわれています。
■ちなみに・・・
coffeeの日本語表記である「珈琲」は、宇田川榕菴が考案し蘭和対訳辞典で使用したのが最初であると言われています。津山藩のあった岡山県には、江戸時代に宇田川榕菴が使用していたコーヒー煮出し器「コーヒーカン」を復元した器でコーヒーを淹れてくれるカフェもあります。

粗品イメージ ※事情により内容が変更になる場合があります
試薬の日クイズ!
全問正解者の中から抽選で39名に、コスモ・バイオオリジナルグッズを含む
粗品をプレゼントします!
当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
【応募期間】3月4日(月)から3月8日(金)まで ※クイズ応募は終了しました。
試薬の日 クイズ <正解回答>
● 1日目(3月4日)
問題: 3月9日は「試薬の日」ですが、これは日本ではじめて試薬という言葉を使った幕末の津山藩医で蘭学者の「宇田川榕菴(うだがわ ようあん)」の生誕日に因んで選ばれました。
さて、この宇田川榕菴、ほかにもさまざまなことをした記録が残っています。
次のうち記録が残っているのはどれでしょう?
a. スキー場の調査をした
b. 温泉の調査をした
c. 鉄道の調査をした
正解:b. 温泉の調査をした
養父・玄真の養生のために、温泉の効能(泉質)を調べており、これが日本で初めて行われた温泉の泉質調査であったといわれています。
● 2日目(3月5日)
問題: 水より比重が大きい試薬は、次のうちどれでしょうか?
a. エタノール
b. 硫酸
c. ヘキサン
正解:b. 硫酸
比重とは、ある物質の密度(単位体積当たり質量)と、基準となる標準物質(液体の場合は水)の密度との比を表したものです。同じ500mL瓶に入った試薬でも、比重によって重さが全然違ってきます。
● 3日目(3月6日)
問題: 「糖化(glycation)」を説明した文章は、次のうちどれでしょうか?
a. タンパク質が糖と結びつくこと
b. 炭水化物が糖と結びつくこと
c. 食物繊維が糖と結びつくこと
正解:a. タンパク質が糖と結びつくこと
糖化とは、タンパク質と糖の結合によって起こる反応で、これによってタンパク質が変性してAGEsという物質ができます。この糖化は体内でも起こっていて、糖化によって蓄積する体内のAGEsが老化を進める物質であることがわかってきています。AGEsが体内のさまざま場所に蓄積すると、やがてタンパク質が本来の役割を果たせなくなり、これが多くの疾病の要因となる、ということが最近の研究で次々と明らかになってきます。
● 4日目(3月7日)
問題: 種なしブドウを作るために使う薬品は?
a. ホルマリン
b. アスタキサンチン
c. ジベレリン
正解:c. ジベレリン
種無しブドウは、ジベレリンという植物ホルモンで処理することによって作られます。一房一房を手作業で処理する、とても手間のかかる作業です。
● 5日目(3月8日)
問題: コスモ・バイオは現在約1,400万品目の試薬類を取扱っていますが、創業当初、一番初めに取り扱った試薬の種類は次のうちどれでしょう?
a. 抗体
b. 細胞培養用培地
c. レクチン
正解:c. レクチン
コスモ・バイオの事業は、1978年に丸善石油(現在のコスモ石油)の一室で誕生しました。初めて取り扱ったのはEYラボラトリーズ社の「レクチン」。丸善石油の社員A氏のもとに、A氏が米国丸善石油で勤務していた頃の元秘書が、生化学者の夫(EYラボラトリーズ社の社長)とともに訪ねてきて、レクチンの日本での販売を相談されたのがきっかけです。






















