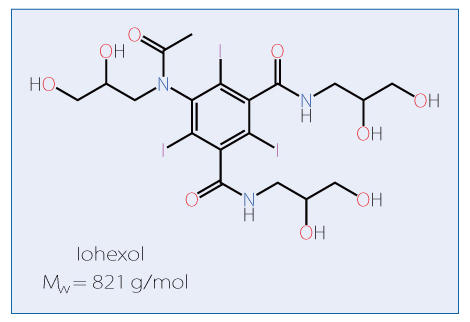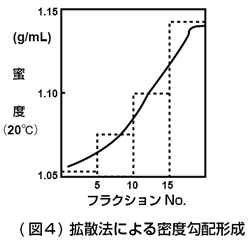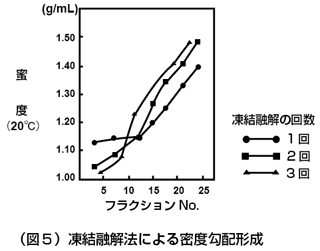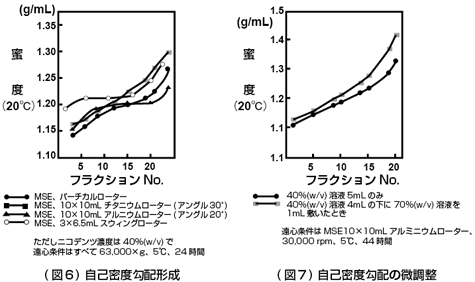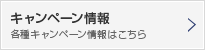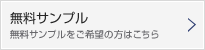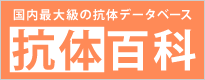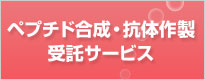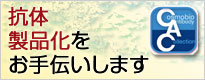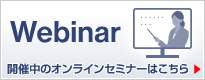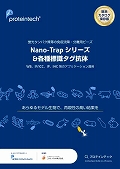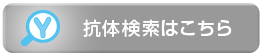I.調製法
1) ニコデンツ溶液の調製法
ニコデンツ粉末を、水または食塩水に凝集塊を作らないようにゆっくり混和しながら加え溶解します。このとき、80% (w/v) 以上の濃度まで溶解でき、密度1.45 g/mLまでの溶液が作製できます。
ホルムアミド、ジメチルホルムアミドには50% (w/v) 、密度1.4 g/mLまで溶解できます。
ニコデンツ濃度と密度の関係を(表1)に示します。
濃度
%(w/v) (mm) |
屈折率
(η)
20℃ |
密度
(g/mL)
20℃ |
浸透圧
(m0sm) |
粘度
(mPas) |
| 0 |
0 |
1.3330 |
0.999 |
0 |
1.0 |
| 10 |
0.122 |
1.3494 |
1.052 |
112 |
1.3 |
| 20 |
0.244 |
1.3659 |
1.105 |
211 |
1.4 |
| 30 |
0.365 |
1.3824 |
1.159 |
299 |
1.8 |
| 40 |
0.487 |
1.3988 |
1.212 |
388 |
3.2 |
| 50 |
0.609 |
1.4153 |
1.265 |
485 |
5.3 |
| 60 |
0.731 |
1.4318 |
1.319 |
595 |
9.5 |
| 70 |
0.853 |
1.4482 |
1.372 |
1045 |
17.2 |
| 80 |
0.974 |
1.4647 |
1.426 |
- |
30.0 |
表1 ニコデンツ溶液の性状
II.密度勾配作製法
密度勾配の作製には、拡散形成法・凍結融解形成法・自己密度勾配形成法・グラジェントミキサーによる密度勾配形成法があります。
1) 拡散形成法
異なる濃度のニコデンツ溶液を遠心管に重層して密度勾配を形成する方法で、18〜24時間で連続的な密度勾配が得られます。尚、拡散時に遠心管を静かに横に倒せば、時間を短縮することが可能です。この方法で4濃度のニコデンツ溶液を使用した場合、直径1 cmの遠心管では、45分間 (20℃) で連続的な密度勾配を得ることができます(図4)。
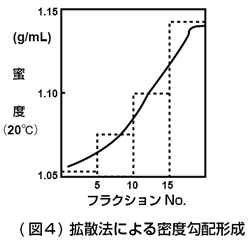
2) 凍結融解形成法
ニコデンツの均等溶液を遠心管に入れ、凍結融解することにより密度勾配を得る方法です。尚、凍結融解を繰り返すことにより、より範囲が広く、連続的な密度勾配を得ることができます。40%ニコデンツ5 mLを使用した場合の密度勾配を、(図5)に示します。
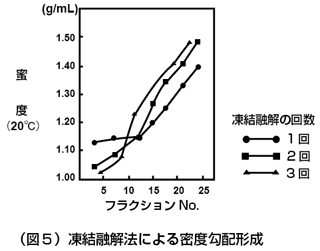
3) 自己密度勾配形成法
ニコデンツの均等溶液を遠心することにより、密度勾配を得る方法です。
尚、使用する遠心ロータの種類・遠心時間・遠心スピード、遠心時の温度・ニコデンツの初期濃度等により、勾配の形成が異なります。(図6)
また、均等溶液の下に少量の高密度溶液を敷いて遠心すれば、微妙な密度勾配の調製が可能です。(図7)
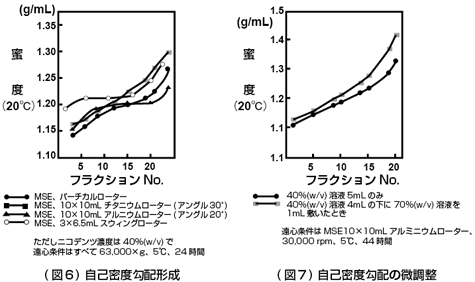
4) グラジェントミキサーによる密度勾配形成法
市販のグラジェントミキサーを使用することにより、理想的な連続密度勾配、または任意の非連続密度勾配を形成することができます。
III.密度の測定
1) 屈折率測定法
勾配の密度を測定する方法として、勾配の屈折率を測定する方法が便利です。ニコデンツ溶液の密度と屈折率には直接関係があります。(表1)
密度(g/mL、20℃)=3.242η−3.323
なお、他の溶質が存在すると屈折率が上昇しますので上記公式を応用する時は屈折率の調製を行って下さい。
2) 吸光度測定法
350 nmまたは360 nmの吸光度からも密度測定が可能です。密度と吸光度の関係を(表2)に示します。
尚、他成分の影響を除くためにブランク補正を行ってください。
Nycodenz®の使用法を記載したアプリケーションが、下記 Axis-Shield社 ウェブサイトにございますのでご参照ください。
濃度
% (W/V) |
密度
(g/mL) |
吸光度 |
| 350nm |
360nm |
| 1 |
1.004 |
0.06 |
0.03 |
| 2 |
0.009 |
0.12 |
0.07 |
| 4 |
1.020 |
0.25 |
0.15 |
| 6 |
1.030 |
0.38 |
0.23 |
| 8 |
1.040 |
0.51 |
0.31 |
| 10 |
1.052 |
0.64 |
0.39 |
| 15 |
1.078 |
0.97 |
0.58 |
| 20 |
1.105 |
1.29 |
0.79 |
| 25 |
1.131 |
- |
0.99 |
表2 ニコデンツの密度と吸光度の関係


























 このページを印刷する
このページを印刷する