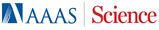- ホーム
- 2007:シグナル伝達の「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」
2007:シグナル伝達の「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」
2007:Signaling Breakthroughs of the Year

Science Signaling, 8 January 2008
Vol. 1, Issue 1, p. eg1
[DOI: 10.1126/stke.11eg1]
Elizabeth M. Adler1*, John F. Foley1, Nancy R. Gough2, and L. Bryan Ray3
1 Associate Editors of Science Signaling2 Editor of Science Signaling
3 Consulting Editor of Science Signaling and Senior Editor of Science, American Association for the Advancement of Science, 1200 New York Avenue, N.W., Washington, DC 20005, USA
2008年から、Science STKE(Signal Transduction Knowledge Environment)はScience Signalingとして誌名を新たにするが、光栄なことに、STKEの長期愛読者の皆様が期待するSTKEならではの特徴は、新誌面にすべて受け継がれている。このようにして、新年をシグナル伝達の「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」とともに迎えられたことを祝したい。年1回の特別号であるこの「ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」では、昨年1年間のなかで最も面白いと思われる研究結果と今後有望な進展について、STKE編集部の各委員と他の著名な細胞シグナル伝達研究者に候補を推薦してもらった。2007年のシグナル伝達の注目すべき進展の推薦者は、Ivan Dikic(ドイツ、ゲーテ大学医学部)、Ravi Iyengar(米国、マウントサイナイ医科大学)、Michael Lenardo(米国、NIH)、Edgar Serfling(ドイツ、ウルツブルグ大学)、Solomon Snyder(米国、ジョンズホプキンス大学)、Eric Vivier(フランス、マルセイユ‐ルミニ免疫学センター)、以上の方々である。このほかにも優れた研究は多数あり、推薦された研究はごく一部であることをご留意いただきたい。例年のごとく、推薦にご協力くださった科学者の皆様に謝意を表し、細胞核のクロマチン状態を制御するシグナルから生物の社会的行動を調節するシグナルに至るまで、幅広い範囲の多数の進展をこの誌面で発表できることに感激を覚える。本年度の研究成果には、既知の免疫学的経路の予想外のメカニズムとこのメカニズムに関係する因子、細胞の分化や発生に関与するプロセスの理解の進展、細胞シグナル伝達経路のダイナミクスの検討、シグナル伝達経路におけるユビキチンや関連分子の普遍性の認識の向上、細胞や生物の記憶にとって重要な翻訳後修飾、末梢感覚の市場を独占した一連のチャネルなどが含まれる。
「遺伝子制御と細胞分化の関係は、シグナル伝達研究における最も魅力的なトピックのひとつだ」と述べ、Edgar Serflingはこの分野に関連する3つの進展を推薦した。まず1つ目の研究では、おそらく最もドラマティックなものであるが、ヒト(1, 2)とマウス(3, 4)の体細胞は、少数(各4個)の「マスター」転写因子からなる決まった小グループによって、多能性幹細胞に再プログラムされることが実証された。再生医学における重要性はさておき、これらの研究は「細胞分化とシグナル伝達現象に対する新しい観点」を提供し、「細胞分化時に生じる分子学的事象の階層性の一部を解明するものだ」とSerflingは述べた。これらの4つの研究は、逆分化するために転写因子の中心的集団を導入した研究であるが、それに対しSerflingが取り上げたもうひとつの研究では、あるひとつの転写因子―Pax5―のコンディショナルな欠失によって、成熟B細胞が未分化造血前駆細胞に脱分化できることが示された(5)。どちらの場合も、非常に限られた数の転写因子が細胞分化に対してどれだけ幅広い影響を与えることができるか説明するものであるが、こうした「マスター制御因子」自身がどのように制御されているのかという問題は、まだ解明されていない。
DNAおよびDNAと相互作用するヒストンタンパク質の両方の共有結合修飾を介して、遺伝子機能がエピジェネティック制御を受けることによって、細胞分裂が繰り返される間中、DNA配列が変化しなくても遺伝子発現の変化が持続することが可能である(図1)。こうしたエピジェネティックな修飾は、DNAとヒストンの会合の変化に応じて染色体領域の転写を可能にするかしないかにかかわらず、発生時に生じる分化のプロセスにとって不可欠であると考えられている。さらに、細胞がより分化していない状態に戻れるのは、こうしたエピジェネティックな「マーク」自体が元に戻れる場合だけである。3つ目の推薦を行うに当たり、Serflingは「初期のマウスの発生現象を制御するヒストンアルギニンメチル化(6)やヒストン脱メチル化(7)など、エピジェネティックな遺伝子制御の特徴づけにおける進展は、『マスター制御因子』の作用を理解する上で役立つだろう」とコメントした。ヒストンアセチル化、リン酸化、ユビキチン化とは異なり、リジンとアルギニンのみで生じるヒストンメチル化は安定であると長い間考えられており、可逆的であることが明らかになったのはこの数年のことである。Michael Lenardoは、細胞シグナル伝達の最近の重要な進展として、Jumonji C(JmjC)ドメイン含有ヒストン脱メチル化酵素ファミリーに属する酵素―2006年にリジンを脱メチル化することが実証され(8-13)、現在では最初の確証的なアルギニン脱メチル化酵素も含むことが明らかになった(14)―によるエピジェネティック制御を推薦した。
図1 遺伝子機能のエピジェネティック修飾は、ヒストンH3テールの翻訳後修飾と関連する。Ac:アセチル化部位、Me:メチル化部位、P:リン酸化部位。A.M. Bode, Z. Dong, Inducible covalent posttranslational modification of histone H3. Sci. STKE 2005, re4 (2005)より転載。
Solomon Snyderもエピジェネティック修飾を取り上げた一人である。とはいえ、Snyderが取り上げたのは、細胞からその子孫へと「記憶」が受け継がれることを可能にするクロマチン修飾ではなく、生物の記憶の形成に関与すると考えられている、成人の海馬ニューロンにおいて生じるDNAメチル化の特異的かつ動的な変化であった。かつて、David Sweattらがヒストンアセチル化は海馬の記憶形成や恐怖条件づけと関連することを示したが、DNAメチル化は主に発生時に生じるプロセスと関連すると考えられていたことに着目し、Snyderは「記憶条件付け開始後数分以内に生じるDNAメチル化の極めて迅速で大きな変化」を示した同氏の研究室(15)からの新しい研究を推薦した。また、Snyderは、恐怖条件づけは「シナプス可塑性タンパク質Reelinをコードする遺伝子と記憶抑制タンパク質PP1(プロテインホスファターゼ1)をコードする遺伝子を含む特異的なDNA脱メチル化の素早い変化と関連する」ともコメントした。
アセチル化は、ヒストンの重要な翻訳後修飾として長い間認識されてきたが、他の細胞タンパク質の機能を制御するという可逆的アセチル化の機能が明らかになったのは、それからしばらく経ってからのことであった。Eric Vivierは、自然免疫反応の活性化について複数の研究を推薦したが、まず1つ目に、ヒストンアセチルトランスフェラーゼCREB結合タンパク質(CBP)によるI型インターフェロン受容体のアセチル化―ならびにその後のアセチル化カスケード―が、インターフェロンaのシグナル伝達に関与することを示した研究(16)を取り上げた。すなわち、受容体リン酸化の役割はよく知られているが、受容体アセチル化もI型インターフェロン受容体を介したシグナル伝達にとって不可欠なようであることから、サイトカイト受容体シグナル伝達に関する既知の理論的枠組みを揺るがすかもしれない。
また、Vivierの選択には、注目すべき進展がみられた免疫学の分野として、Toll様受容体(TLR)シグナル伝達も含まれた。Toll様受容体(TLR)は、病原体に関連する手掛かりを認識し、自然免疫反応を開始する。ところが、個々のTLRがヒトを病気から守る上で冗長的な役割を演じているのか、非冗長的な役割を演じているのかは明らかでなかった。Vivierが推薦した研究では、dsRNAを認識するTLR3の欠損は単純ヘルペスウイルス1型脳炎に対する感受性と特異的に関連し、そのため、この疾患に対する防御機構において非冗長的な役割を担うことが示された(17)。また、Vivierは、リガンドがどのように受容体二量体化やシグナル伝達を促進するのかを表すモデルを導出した、リガンド結合TLRの結晶構造に関する最初の2報(18, 19)にも着目した。
ウイルス感染に対する応答に関与するのはTLRだけではない。ウイルスに感染した細胞は、自然免疫反応を開始するCARD含有DExD/HボックスRNAヘリカーゼによって検知されるRNAを産生する。Vivierの最後の推薦は、ウイルス感染が内因性self-RNAを切断し、免疫反応を増幅、存続させる低分子RNA産物を生成するエンドリボヌクレアーゼRNaseLの活性化をもたらすことを示した研究である(20)。このため、その後の免疫反応はnonself RNAへの直接的な曝露によって開始する反応を上回り、この結果は抗ウイルス療法において有意義となるだろう。
免疫学の分野における最後のブレークスルーは、20年もの間、炎症や免疫反応にとって不可欠な役割を担うと考えられてきた、核因子kB(NF-kB)の経路に関するものである。各種の刺激によって、NF-kB転写因子ファミリーメンバーの核への移行が誘導され、そこでホモ二量体化またはヘテロ二量体化を受けて標的遺伝子の転写を制御する。Michael Lenardoらは、NF-kBがDNAと相互作用するメカニズムをさらに解明し、無関係のタンパク質―リボソームタンパク質S3(RPS3)―が、NF-kB複合体の未知のサブユニットとして機能するという予想外の知見を見出した(21)。
多くの場合、シグナル伝達のブレークスルーは他の分野の研究と同様、新しい技術の採用によって決定される。本年推薦された注目に値する2つの進展は、関与するプロセスの画像化を可能にするライブセルイメージング法によって、細胞シグナル伝達経路のダイナミクスを解明したものである。Lenardoは、リアルタイム共焦点顕微鏡法を用いて、原形質膜においてWntがリン酸化Wnt共受容体低密度リポ蛋白受容体関連タンパク質6(LRP6)やWntシグナル伝達経路の他の構成要素を含有する高分子タンパク質複合体の凝集を誘導することを示した研究を推薦した(22)。この研究は、驚くべき結論を導き出した。LRP6の活性化と「LRP6-シグナロソーム」の形成が、Dishevelled(Wntシグナル伝達経路において、共受容体LRP6の下流で機能すると考えられていた足場タンパク質)に依存するというのである。Ivan Dikicは、Forster共鳴エネルギー移動(FRET)に基づく手法を用いて、生細胞の酵素活性を画像化し、上皮成長因子受容体(EGFR)シグナル伝達におけるチロシンホスファターゼPTP1Bの空間的制御の役割を調べた研究を推薦した(23)。
また、Dikicは、「ユビキチンとユビキチン様分子が多くのシグナル伝達過程において中心的役割を担うという新しい概念」に貢献したいくつかの研究にも言及した。2006年度の研究は、共役モノユビキチン化の分子学的基盤と機能的帰結を理解するための基盤を築いたが(24-26)、2007年にDikicの研究室から報告された研究では、共役モノユビキチン化にはE3リガーゼは必要でないが、その代わりに、E2酵素もこの翻訳後修飾を仲介できることが示された(7)。Dikicは、「これらの2種類の共役モノユビキチン化(E3依存性のモノユビキチン化とE2を介するモノユビキチン化)は、機序的には明らかに異なり、前者は成長因子によって活性化され、後者は不活化細胞における恒常性メカニズムとして機能する。それにもかかわらず、どちらも標的タンパク質の機能的不活化をもたらす」とコメントした。Dikicの最後の推薦は、細胞シグナル伝達に関与する主要因子としてのユビキチンとユビキチン様タンパク質という同じテーマに関するもので、オートファゴソームの形成におけるATG8―「古典的なユビキチン機構」を用いて、ホスファチジルエタノールアミンとの抱合を介して膜に会合するユビキチン様タンパク質―の役割を調べた研究であった(28)。
Ravi Iyengarは、推薦を行うにあたり、「本年はシグナル伝達のメカニズムが生物の行動にどのように寄与するかを理解する上で、まさに大当たりの一年だった。この情報はすべてモデル生物から得られたものだ」とコメントした。興味深いことに、シアノバクテリアの概日振動子は、in vitroにおいて、転写や翻訳に関連するフィードバックループには依存せずに、わずか3つのタンパク質によって再現できた(29)。Iyengarの最初の推薦は、この系の基礎を成すメカニズムを解明した1組の研究で(30, 31)、これらの研究は「積み重ねられた1組のフィードバックループとして構成される共役リン酸化‐脱リン酸化反応(細胞シグナル伝達の不可欠な要素)が、概日振動子としてどのように機能できるのかを非常に上手に示している」とコメントした。Iyengarの2つ目の推薦は、同氏が「ネットワークモチーフの一部である個々のニューロンにおける分子機能が生物の行動をどのように引き起こすかを示した、最初のマルチスケールの相関」と評した研究で、線虫(Caenorhabditis elegans)の食物探索行動の仲介に関与する回路を調べたものである(32)。最後に、Iyengarは「ロボット型のゴキブリも一種のモデル生物だ」と論じ、フェロモンで被覆した小型ロボットがゴキブリの集団に受容され、さらにこの集団の行動を変化させられることを示した研究を「細胞外シグナルが集団環境において社会的同一性を与えることを強力に裏付けた」と評し、推薦した(33)(図2)。Snyderは、シグナル伝達メカニズムと行動を関連づけた、もうひとつの進展を取り上げた。メントール受容体TRPM8を欠損するマウスの研究によって、マウスは寒冷を感知する能力をほとんど完全に失い、低温に適切に応答できないことが示されている(34-36)。メントール受容体TRPM8が寒冷の生理学的受容体であることを決定的に同定した研究を推薦するにあたり、Snyderは「TRPチャネルによって我々のすべての末梢感覚が説明される」「予想以上に素晴らしい」結果であると述べた(図3)。また、これらの結果は「感覚シグナル伝達に対する基本的な重要性」があるだけでなく、「創薬においても製薬業界が見落とせない大きな意義がある」とも付け加えた。
図2 フェロモンで被覆した小型ロボットに近づくゴキブリ。(33)より転載。
図3 TRPチャネルの系統樹およびトポロジーと、これらのチャネルにおける重要な位相幾何学的部位。CaM:カルモジュリン、EWKFAR:TRPボックスの1文字アミノ酸コード(Glu-Trp-Lys-Phe-Ala-Arg)、PDZ:タンパク質‐タンパク質相互作用の結合ドメイン。B. Nilius, T. Voets, J. Peters. TRP channels in disease. Sci. STKE 2005, re8 (2005)より転載。
本年度のシグナル伝達のブレークスルーをお楽しみいただけただろうか。もし、皆様がこれらの素晴らしい論文を集めたこの記事を研究仲間に推薦してみようとお考えであれば、新誌名「Science Signaling」が皆様にとってより馴染みのあるものになれば幸いである。