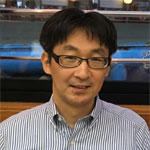
分子生物治療研究部 部長
清宮 啓之 先生
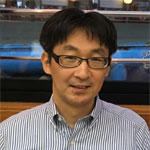
日本人の2人に1人が生涯でがんに罹患し、3人に1人の死因ががんである、と言われるようになってからすでに10年以上が経つ。65歳以上の人口の割合が全人口の21%以上を占める「超高齢社会」を迎えた我が国においては、加齢とともに罹患率が増加するがんをいかに予防し、いかに根治し、あるいはいかにがんと共生すべきかが大きな課題であり、これらは2014年に定められた「がん研究10か年戦略」(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)の基本骨子となっている。がんの標準療法としては、外科療法、放射線療法、薬物療法の3本柱に加えて、2018年のノーベル生理学・医学賞の授賞対象となった、免疫療法が第4の治療法として位置づけられている。薬物療法はさらに、増殖性の高いがん細胞を攻撃する細胞傷害性の抗がん剤(化学療法)、がんに特異的な分子変化をピンポイントで攻撃する分子標的治療薬の2つに大別される。米国癌学会(American Association for Cancer Research: AACR)が毎年発行しているCancer Progress Report の2018年最新版では、がんの治療は外科療法、放射線療法、化学療法、分子標的療法、免疫療法の5本の柱で成り立つとされている1)。これらの中でも分子標的治療は特に、がん個別化医療(プレシジョン医療:precision medicineとも呼ばれる)を実践するための中心的位置づけにあるといえる。
がんゲノム解析の飛躍的進展に伴い、さまざまながん種のそれぞれに特徴的なゲノム異常のランドスケープが明らかとなり、発がんおよびがんの悪性化を牽引するドライバー遺伝子(がん遺伝子およびがん抑制遺伝子)の詳細なリストを一望することができるようになってきた。これらのゲノム異常は、例としてメチル化修飾酵素遺伝子の異常により、同じくがんに特徴的なエピゲノム異常(DNAメチル化やヒストン修飾の異常)を引き起こすなど、まさにがんの病因(etiology)を紐解く原点であるといえる。特に重要で基本的なポイントとして、がん細胞は正常細胞と異なり、ドライバー遺伝子に対する依存性(がん遺伝子依存性:oncogene addiction)を獲得していることが多い。したがって、がんのドライバー遺伝子とそれに対するがん細胞の依存度を理解することは、当該ドライバー遺伝子を有するがんの脆弱性を理解することと表裏一体である。治療的視点に立てば、ドライバー遺伝子産物はがんに選択性の高いアキレス腱、すなわち分子標的(molecular target)であり、その働きを抑える小分子化合物および免疫グロブリン(抗体)製剤が分子標的治療薬として広く用いられてきた。
分子標的治療薬のうち、小分子化合物としてはキナーゼ阻害剤、プロテアソーム阻害剤、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤、メチル化酵素阻害剤、ポリ(ADP-リボシル)化酵素(PARP)阻害剤などがある。これらの特異的標的分子のうち、キナーゼ(EGFR、ALK、ABL、BRAF、MEK、PI3K、CDK4/6など)はドライバー遺伝子の代表例であり、それぞれのキナーゼ阻害剤(抗EGFR阻害剤ゲフィチニブや抗ALK阻害剤クリゾチニブ、抗ABL阻害剤イマチニブなど)はがん治療特異性が最も高いレベルの薬剤として位置づけられている。一方、PARP(PARP-1およびPARP-2)はがん抑制遺伝子産物であるBRCA1もしくはBRCA2などの相同組換え修復因子と合成致死(synthetic lethal)の関係にあり、オラパリブなどのPARP阻害剤はこれらの因子の「不在性」を間接的な標的とするユニークな薬剤である。抗体の分子標的治療薬としては、細胞膜貫通型のタンパク質もしくは分泌性の増殖因子などを認識するものに大別され、抗EGFR抗体セツキシマブのように受容体型チロシンキナーゼの働きを抑えるものや、抗VEGF抗体ベバシズマブのように腫瘍内の血管新生を抑えるものなどがある。抗体医薬の場合は、抗原である標的分子の働きを抑えるばかりでなく、抗体依存性細胞傷害(antibody-dependent cellular cytotoxicity: ADCC)や補体依存性細胞傷害(complement-dependent cytotoxicity: CDC)といった生体固有の防御反応を介して、あるいは殺細胞性化合物や放射性同位元素を抱合したかたちでがん細胞を積極的に殺傷する性質のものもある。それぞれの分類の仕方にもよるが、世界でこれまでに、50種類以上の小分子化合物および30種類以上の抗体薬ががん分子標的治療薬として承認されている2)。
がん分子標的治療薬には、初期(第1〜第2)世代の分子標的治療薬に耐性となった変異型標的分子に対して有効な、高次(第2〜第3)世代の薬剤(薬剤耐性T790M変異型EGFRに有効なオシメルチニブなど)も含まれるが、治療薬が存在する(=actionableという)標的分子の絶対数も増えてきている。したがって、例えば肺がんの場合、EGFR変異陽性であればEGFRチロシンキナーゼ阻害剤、ALK転座陽性であればALKチロシンキナーゼ阻害剤、といった具合に、個々の患者に適した治療薬を選択することが可能である。このことはすなわち、分子標的治療薬の選択には、それぞれのがんが当該標的分子(遺伝子の変異もしくは増幅)を有しているかどうかを正確に判断する「コンパニオン診断」が必要であることを意味している。上述のように、actionableなドライバー遺伝子のレパートリー数が増えてきた現在においては、検査の時間と費用を抑えるために多数のドライバー遺伝子を同時かつ網羅的に検出する、がん遺伝子パネル検査が有用である。米国ではすでに、MSK-IMPACTやFoundationOneといった遺伝子パネル検査が診療方針の決定に活用されている。例として、MSK-IMPACTのパネル検査を受けた患者のうち、40%の患者はすでにある何らかの適切な治療薬を選択することができ、10%の患者は進行中の新薬治験に入る機会を得ている。これは、治験中の薬剤も含めれば総体として約半数の患者にactionableな選択肢を提供する一方で、残りの約半数の患者にはこれらの薬剤を無益に投薬せずに済んでいる、ということを意味する。我が国においても、このようなクリニカルシークエンス情報に基づく「がんゲノム医療」を推進するため、2018年4月から全国11か所の医療施設が「がんゲノム医療中核拠点病院」として、さらに100か所の施設が「がんゲノム医療連携病院」として指定されている。
がんゲノム医療のパネル検査で調べられる被検遺伝子数は数十から数百と、施設や検査パネルによって差はあるが、いずれにしてもドライバー遺伝子の全てを網羅しているわけではない。分子標的治療薬のレパートリーは未だ限定的なものにとどまっており、アンメットメディカルニーズが多数存在している。そのようなニーズに応える主役はやはり、分子標的治療および免疫療法であろう。分子標的治療研究における今後の課題をいくつか挙げると、第一に、薬剤耐性の問題がある。様々な臓器がんに対するキナーゼ阻害剤の奏効割合はおよそ40〜90%と高い値を示しているが、もともと不応性の症例が一定の割合で存在することに加えて、肺がんや悪性黒色腫など、たとえ奏効してもその持続期間が10か月にも満たないがんも多い3)。耐性がんを克服する上では、がんの複雑性、具体的にはクローン進化やがん幹細胞の存在などによる、がん細胞集団の不均一性(heterogeneity)および可塑性(plasticity)を理解することが重要である。第二に、RASのような非キナーゼ性のシグナル伝達因子や、MYCのように機能ドメインが大きく、小分子化合物では制御しにくい転写因子など、歴史的に超メジャー級のドライバー遺伝子でありながらも、創薬フィージビリティ(druggability)が低い標的分子が存在する。これらを攻略しうる有望なアプローチとしては、PROTACやSNIPERなどの特異的タンパク質ノックダウン技術が注目されている4)。第三に、adenomaからcarcinomaに至る多段階発がん過程を経て発生する大腸がんのように、複数のドライバー経路が活性化することで、経路間の相互排他性(mutual exclusivity)が認められなかったり、addictionの程度が弱い多数の遺伝子変異が同時多発的に生じたりする場合(いわゆる“long-tail”タイプ)は、治療標的として有効なアキレス腱を一義的に掴むことが困難である。そのような場合、ワールブルク効果(有酸素下でもミトコンドリアでなく解糖系でATPを産生する現象)に代表されるように、がんに特徴的な代謝のリプログラミング様態を標的とした創薬などが試みられている。さらに、ドライバー遺伝子が不明確であっても、ゲノム変異の絶対数(tumor mutation burden: TMB)が多いがんでは免疫細胞によって認識される新生抗原(neoantigen)の産生確率が高まることから、抗PD-1抗体などの免疫チェックポイント阻害薬が有効であることが示されている(ご存じの通り、2018年、京都大学の本庶佑先生がノーベル生理学・医学賞を受賞されている)。とりわけ、マイクロサテライト不安定性(microsatellite instability-high: MSI-H)を有するがんやミスマッチ修復機構を欠損した(defective mismatch repair: dMMR)がんではTMBが大きいため、免疫チェックポイント阻害薬が有効である。2017年5月、米国食品医薬品局FDAがMSI-H/dMMR固形がんに対する治療薬として、抗PD-1抗体ペムブロリズマブを臓器横断的に迅速承認したことは記憶に新しい5)。これは、「適応癌腫(がん種)」という従来の考え方を打ち破る、画期的な出来事であった。一方、個々の創薬シーズの探索段階に立ち戻れば、データサイエンスや人工知能(AI)を動員した標的分子および薬効予測バイオマーカーの探索と検証、ゲノム編集やオルガノイド・患者由来ゼノグラフト(patient-derived xenograft: PDX)といった先端技術を駆使した薬効評価系など、開発の効率と精度を高めるためのストラテジーが深化してきている。
ところで、分子標的治療とその総合実装体制としてのがんゲノム医療は、医療経済とも密接に関係している。新薬の相次ぐ登場に伴い、がん薬物療法のコストは高騰化しており、国民皆保険を適用している我が国の医療経済は危機にさらされている。そもそも、革新的新薬は、たとえ日本発のシーズであっても最終的に外資系製薬会社に導出されて開発されることが少なくなく、年間2兆円以上にも達する医薬品の貿易赤字は看過しがたい。国外開発や国際共同治験など、海外との協働体制が高効率な新薬開発を実現してきた側面がある一方、我が国独自の国家戦略をいっそう強化・推進していくことが不可欠である。いま、国内で創出された基礎研究成果をシーズとした、本邦発のがん創薬が切望されている。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO