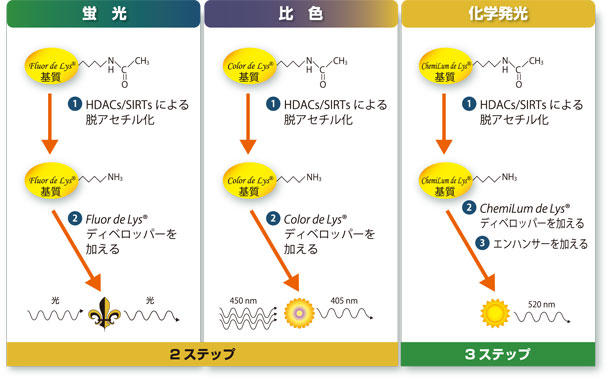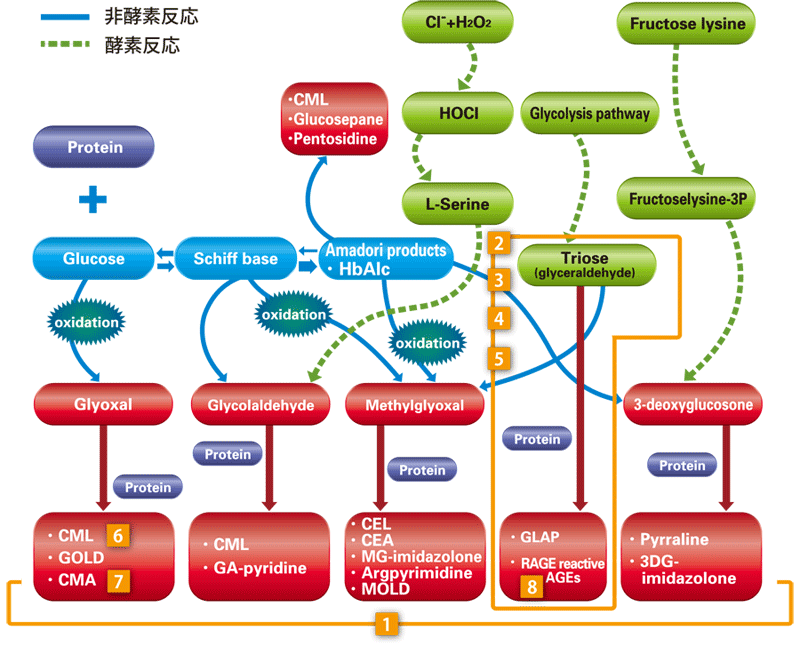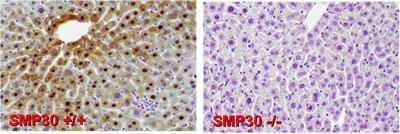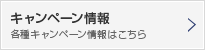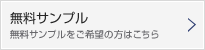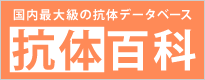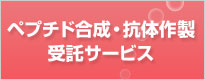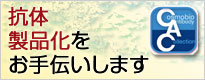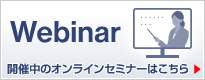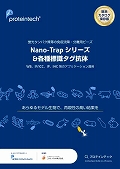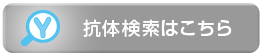広島大学大学院医歯薬保健学研究科・細胞分子生物学研究室
田原栄俊 先生
老化研究は、加齢の原因の多面的解明とともに、細胞レベルでの分子メカニズムが進んでいる。ゲノム解析と加齢疾患との関係や、細胞レベルでの酸化ストレスによる細胞老化誘導メカニズムなど多様である。大規模なコホート研究や双子を用いたツインズ研究などから、加齢の要因として環境因子が重要な因子であることが明らかになっている。例えば、ツインズの女性で喫煙と非喫煙では明らかな老化の進行に違いが見られている。環境因子による加齢との関わりを解明する上で重要な要因は環境因子であるが、その要因の全貌を明らかにするのは困難である。食生活による違いや睡眠などの環境因子も大きな要因である。食生活では、カロリー制限が加齢の抑制と寿命の延長に寄与していることが知られている。睡眠との関係で は、サーカディアン・リズムと加齢との関与が注目されている。また、活性酸素 (ROS) などの蓄積は、生体内での加齢促進の大きな要因であることも知られている。最近では、緑内障発症との関与が報告されており、生体内における ROS シグナルの解明は、加齢疾 患の発症機序を知る上で鍵となる可能性がある。近年急速に進むゲノム解析では、疾患の罹患率や加齢との関わりが示唆される遺伝子なども明らかになっている。
サーカーディアン・リズムと老化
2017年のノーベル生理学・医学賞は、サーカディアン・リズム(Circadian Rhythms, 体内時計)を生み出す遺伝子とそのメカニズムの発見で Jeffrey C. Hall 博士(米ブランダイス大学)と Michael Rosbash 博士(米ブランダイス大学)、Michael W. Young 博士(ロックフェラー大学)の3氏に授与された。サーカディアン・リズムは、睡眠とも密接に関与し、高齢化社会の大きな課題である認知症とも密接に関与している。睡眠や様々な活動を含む 24 時間のリズム変化がどのように制御されているのか不明であったが、3氏は、体内時計としてサーカディアン・リズムが存在すること、それに関わる遺伝子として、per (period) 遺伝子やtim (timeless) 遺伝子が存在していることを明らかにした。さらに、近年、老化現象や認知症などの加齢疾患でもサーカディアン・リズムとの関わりが明らかになっている。今後、これらの遺伝子やサーカディアン・リズムを制御する遺伝子と加齢の制御機構や加齢疾患との関わりの解明が期待される。
◆カロリー制限と老化
カロリー制限による加齢疾患の予防と寿命の延長が知られているが、その分子機構の解明は十分ではない。最新の報告では、カロリー制限による寿命延長において、加齢によるDNA メチル化の関与を調査した結果、DNAメチル化、特に CpGアイランド (CGIs) のメチル化は、加齢に伴って増加し、がんや糖尿病などの進行に関与することが示唆されている1)。しかも、カロリー制限によって、DNA メチル化変動が遅延することを明らかにしており、今後、DNAメチル化変動と様々な加齢疾患との関係を明らかにする上で重要なバイオマーカーとなる可能性を秘めている。
◆加齢におけるゲノム解析とコホート研究
加齢現象は、ゲノム内の遺伝子の個体差と共に、前述の様々な環境因子が複合的に関わるものである。その為、細胞レベルから疾患の罹患率、そして寿命との関係を総合的に明らかにする必要がある。分子生物学的研究のみならず老化に関係する疾患と臨床データとの統合的な解析が重要であり、加齢研究においては、メタアナリシスと呼ばれる統計学的手法を用いた研究が有効である。近年、遺伝子検査などで用いられる SNPs 解析データもその重要な解析データとなるが、解析者によって結果が異なるなどの報告もあり、その解析手法を十分吟味する必要がある。例えば、最近のメタ解析の報告では、HLA-DQA1/DRB1 の SNPs は、寿命を0.6年増加させ、LPA の SNPs は、寿命を0.7年減少させるといった、SNPs と寿命との関わりが報告されている2)。さらに、冠動脈疾患、肺がん、II型糖尿病などの疾患や喫煙量は、死亡率と強く相関することが明らかになっている。冠動脈疾患、肺がん、II型糖尿病などは、染色体の末端にあるテロメアの短縮とも強く相関することが知られている。テロメアの末端には、Gテールとよばれるテロメア一本鎖 DNAが数百塩基存在する。我々は、このテロメア Gテールの短縮が、冠動脈疾患や腎不全にともなう心血管イベントの誘発、大脳白質病変による脳 梗塞や認知症のリスクと関係していることを明らかにしている3)。腎不全における研究では、透析患者の末梢血を採取し、前向き研究 を行った結果、心血管イベントの誘発と発症前の Gテール長の短縮との相関を見いだしたことが、加齢疾患の誘発におけるテロメア Gテール長の短縮による染色体の不安定化が加齢疾患に結びついているものとして注目している4)。
◆最後に
老化研究は、細胞レベルでの研究と共に、加齢疾患の発症や健康寿命との関連も明らかにしていく必要がある。多面的な環境因子が加 齢に関わっている中で、これまでに研究が進められている主要な環境因子(喫煙や食事など)でのコホート研究に加えて、これまでに無関係と思われいる因子にも着目した解析が重要かもしれない。においの刺激で、認知症が改善されることなども報告されており、 生活する温度やその他の外的刺激の度合いなど、加齢の解析がより複雑になる可能性がある。今後は、最新の分子生物学的研究法と共に、多面的な環境要因の解析を複合的に解析するためにも人工知能を用いて解析するなど、新しい試みが期待される。























 このページを印刷する
このページを印刷する