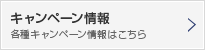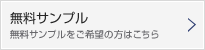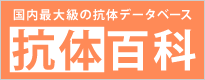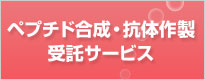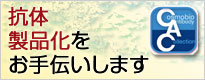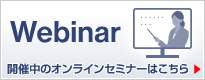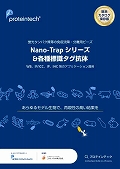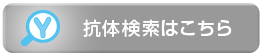我々ヒトも含めた全ての生物は全て蛋白質、糖質、脂質などの物質で構成されています。しかし、生物の最も不思議な点は物質で構成されているにもかかわらず、この物質が栄養素として取り込まれ生物の構成要素となってからそのままとどまるのではなく、ある一定の時間経過後に分解され排泄される、つまり、生物は常に物質の代謝という流れの中に存在しているということです。生物は物質で構成されているにもかかわらずこの物質が常に入れ替わっていることになり「生物の本質とは何か」という疑問が浮上してきます。セントラルドグマ説によると生物の設計図はゲノムにAGTCの4つの塩基を用いて膨大なデータが記憶され保存されており、必要な時にこの情報から蛋白質を作り出し生命活動をしているとされていますが、不思議なことに、このゲノムも物質であることには変わりなく同じように代謝されています。
 続きを見る
続きを見る
▼ 折りたたむ
■ 老化とは?
多細胞生物体における個体の老化は、Advanced Glycation End Products:AGEsの蓄積という新しい概念でとらえられています。AGEsとは蛋白質と糖が同じ場所に存在すると温度と時間経過だけで自動的に反応してできてくる物質の総称です。蛋白質も糖も生命体にとっては必要不可欠な物質で常に食事から摂取しています。つまり生物は生存する上でAGEsの生成と蓄積(=老化)が隣り合わせになっていることになります。近年、AGEsの生成を抑制することで老化を遅らせる物質の探索が進んでいます。方法としては?糖質の摂取を減らす、?腸管からの糖の吸収を抑制する、?腸管から取り込まれ血中に運ばれた糖をインスリンの働きにより肝臓、および筋肉に直ちに貯蔵する、?蛋白質の糖化反応を抑制するなどの方法論が考えられています。
今後は生体内に存在するAGEsがどのように代謝されるかがより重要視されてくると思われます。生体はもともとAGEsの分解、排泄、除去の機能を持っているわけなので、この機能を強化する研究および物質探索も重要になっていると思われます。
■ 多細胞生物体を共生細菌もふくめた超生命体として理解する
近年メタゲノム解析などの急速な普及により、多細胞生物体に寄生(共生関係)している細菌の全貌が明らかになりつつあります。これら一連の研究から、共生関係である細菌の存在が宿主の健康状態に大きな影響力を持っていることが次々と明らかになってきています。特に今回のテーマである代謝を論ずる場合でも宿主の細胞のみの代謝だけではなく、宿主に寄生している細菌(特に腸内細菌)の代謝を含めて総合的に判断しなければなりません。
ヒト1人の場合、ヒト細胞60兆個に対して、腸内細菌は100兆個を占め、ヒトという生命体には、ヒト細胞と細菌の160兆個の集合体からなる超生命体(Superorganism ;ノーベル生理学・医学賞受賞者Joshua Lederberg, が提唱)として食の機能性や医薬品の評価などを考えてゆく時代はすでに到来していると言っても過言ではありません。この超生命体という概念が大きくクローズアップされたのが人工甘味料の存在であると考えられます。これまで腸内細菌を無視し、宿主側のみで見ると、人工甘味料は確かに宿主の腸管からは吸収されにくく、おいしく食べれて太らない、糖尿病を防ぐとかなど言われて巷ではカロリーゼロを謳った飲料が一世風靡していたのは記憶に新しいところです。しかし、近年の研究で一部の人工甘味料は腸内フローラを大きく乱していることが次々と分かってきました。腸内フローラを乱しているのは食品、飲料だけではなく医薬品でも腸内フローラを乱していることも次々に明らかになってきています。幼少期にバンコマイシンという抗菌薬の使用によって、その後のぜんそくのリスクが高くなるなどの研究報告も出てきています。
■ 共生進化論
多細胞生物体を、宿主と共生細菌との総和としてとらえる、「超生命体の概念」を論ずるときLynn Margulis(1938年3月5日〜2011年11月22日)の存在も語る必要があります。進化論といえば教科書的にはCharles Robert Darwin を思い起こされるかと思いますが、Lynn Margulisの提唱する共生進化論はその時間的スケールの圧倒的な大きさから、いまやDarwin進化論を凌ぐこととなりました。Lynn Margulisの提唱する共生進化論は地球生命体発生の時点からヒトをはじめとする動物も含めて共生進化した、つまり我々動物も含めて微生物から進化したと唱えたのです。Lynn Margulisの言う最初の地球生命体出現から現在のような生物多様性が共生進化的に進んできたことを考えると、我々、多細胞生物体も栄養物の吸収経路である腸管(特に大腸)に多くの嫌気性微生物をいまだに養い(多細胞生物体は微生物に場を供給しているとする考えもある)、地球生命体の中で、超生命体として共に代謝の流れの中にあることを思うと感慨深いものです。
■ 再生医療におけるステムセル
近年ES、iPSおよび組織幹細胞であるMesenchymal Stem Cells:MSCなどを用いた再生医療が大きく取り上げられています。しかし、忘れてならないのはこれら何にでもなるステムセルを生体内に投入しても生体内は細胞の新陳代謝も含めた代謝の流れの中にあるということです。多細胞生物体が持つ組織の場の概念そしてその場自身が代謝の流れの中にあるにもかかわらず、その場が再生して行くサイエンスが待たれるところです。
平 敏夫 コスモ・バイオ(株)札幌事業所























 このページを印刷する
このページを印刷する